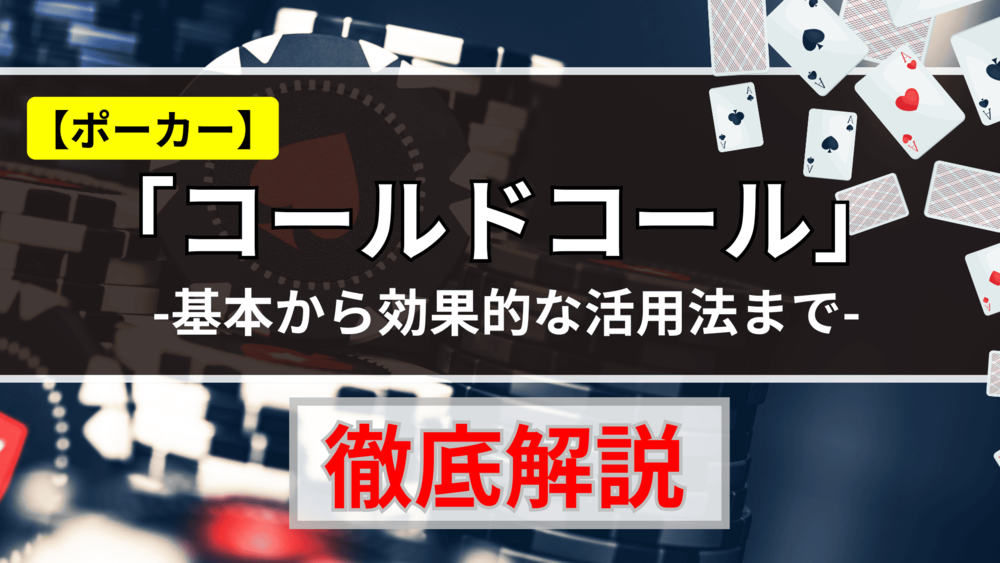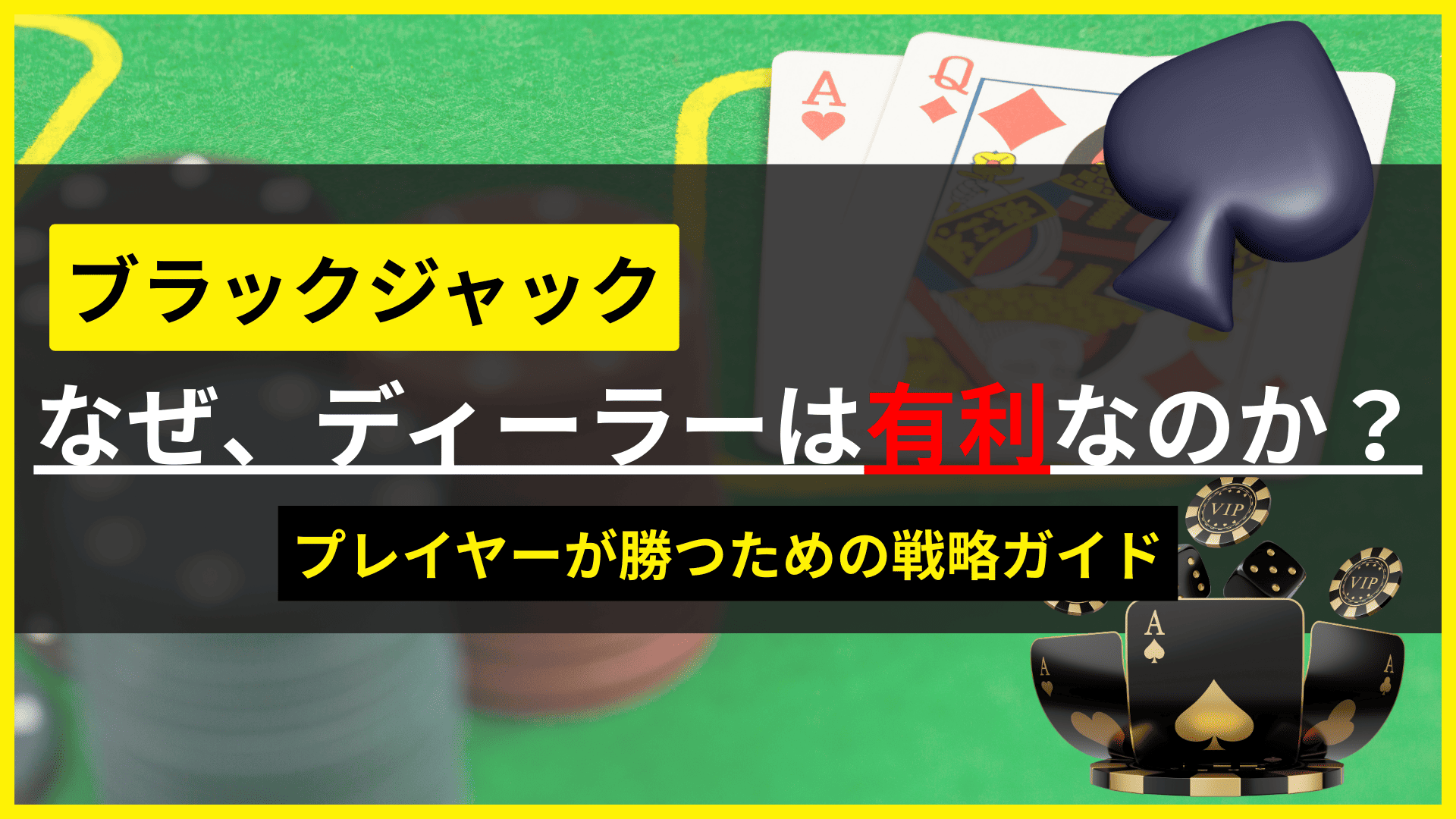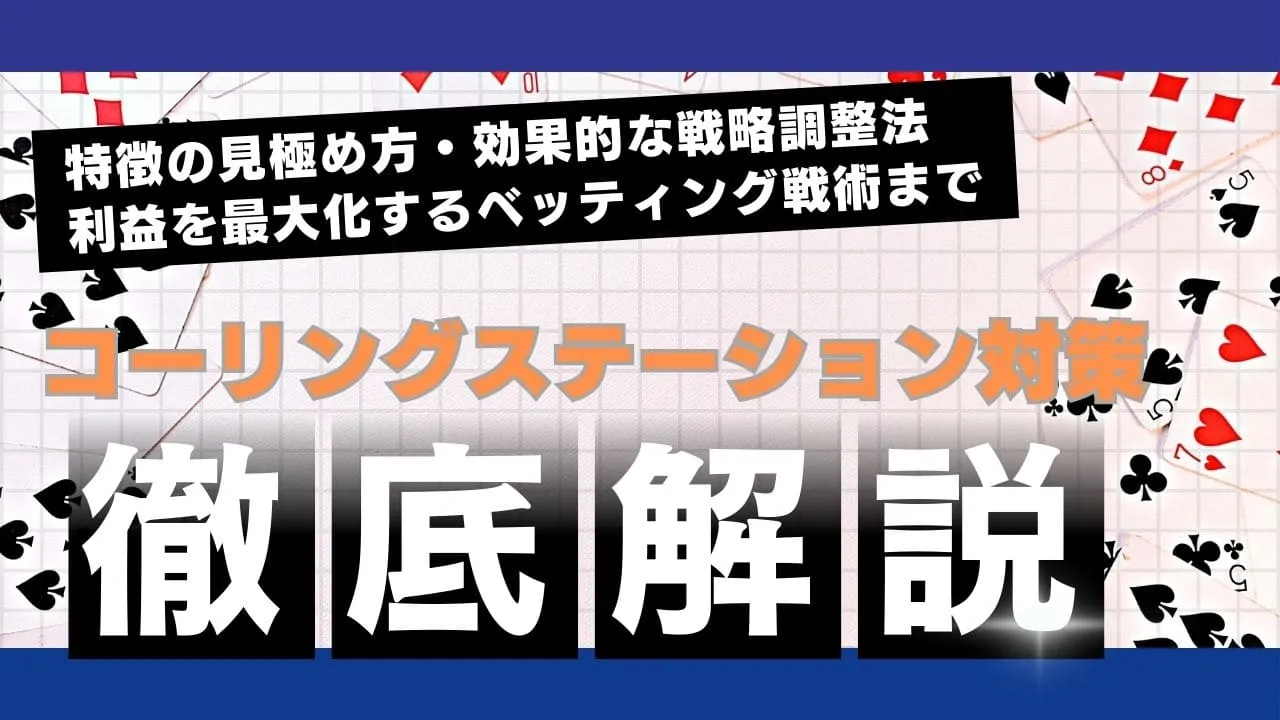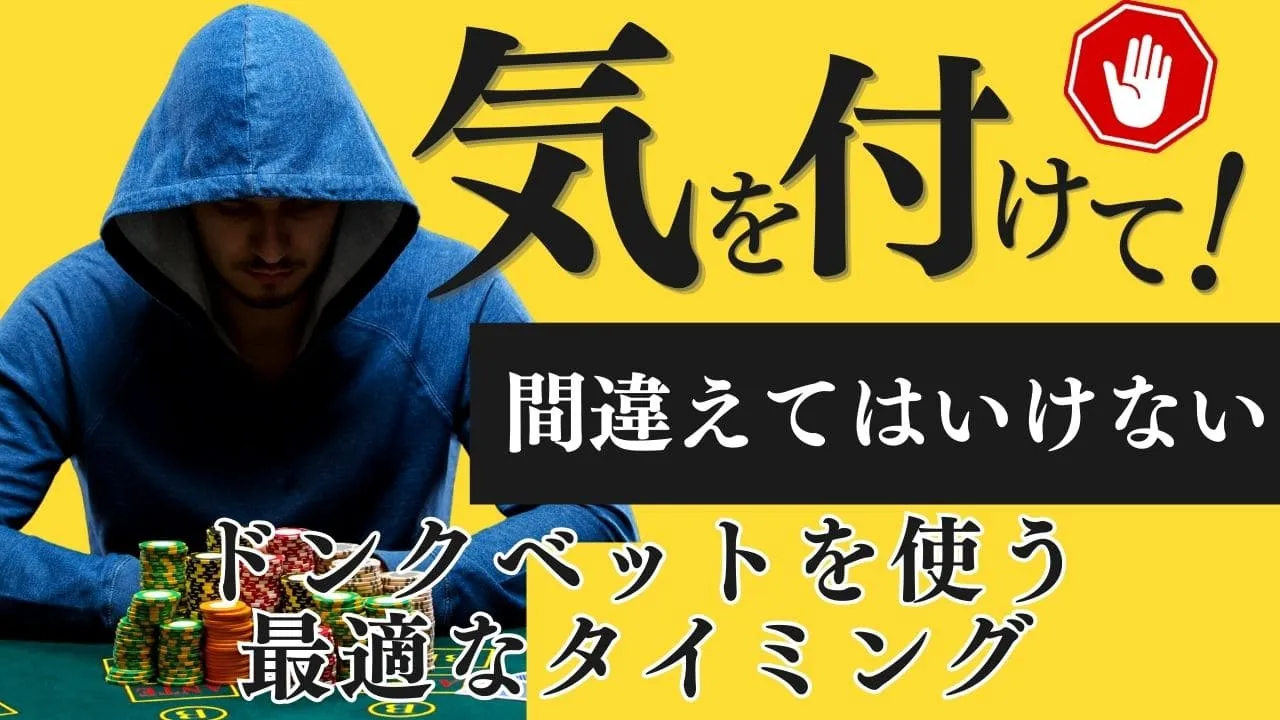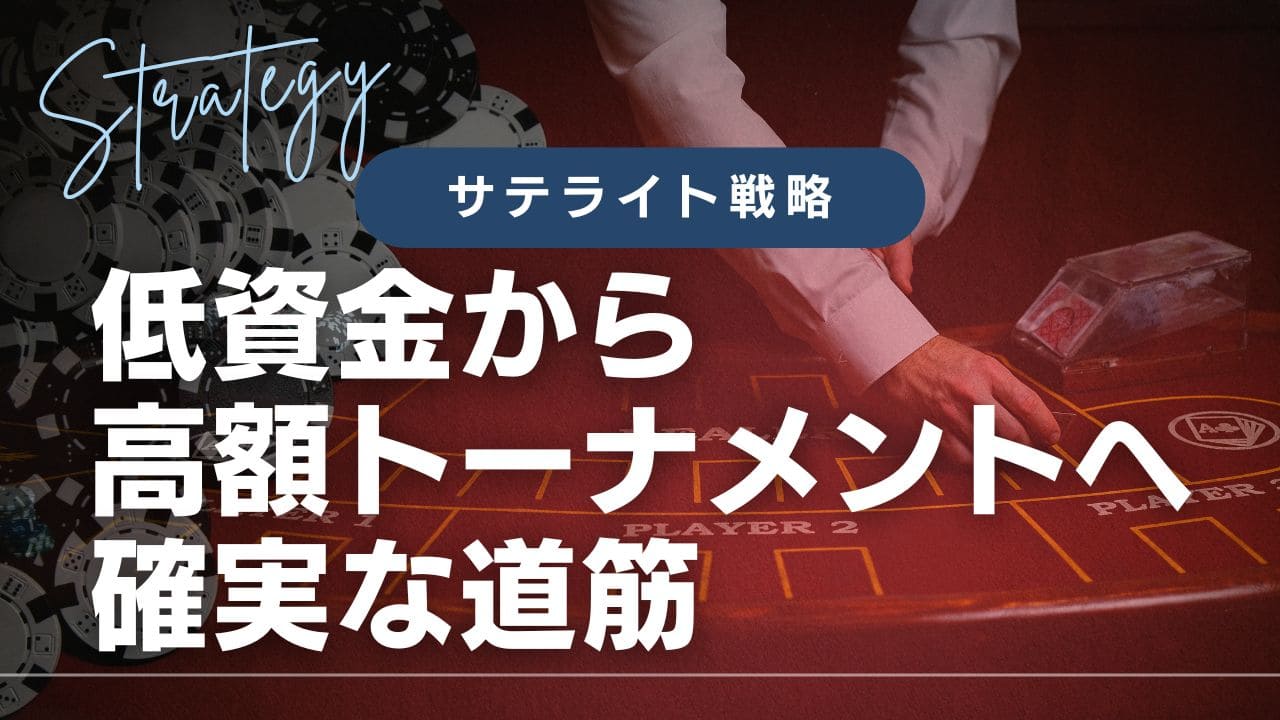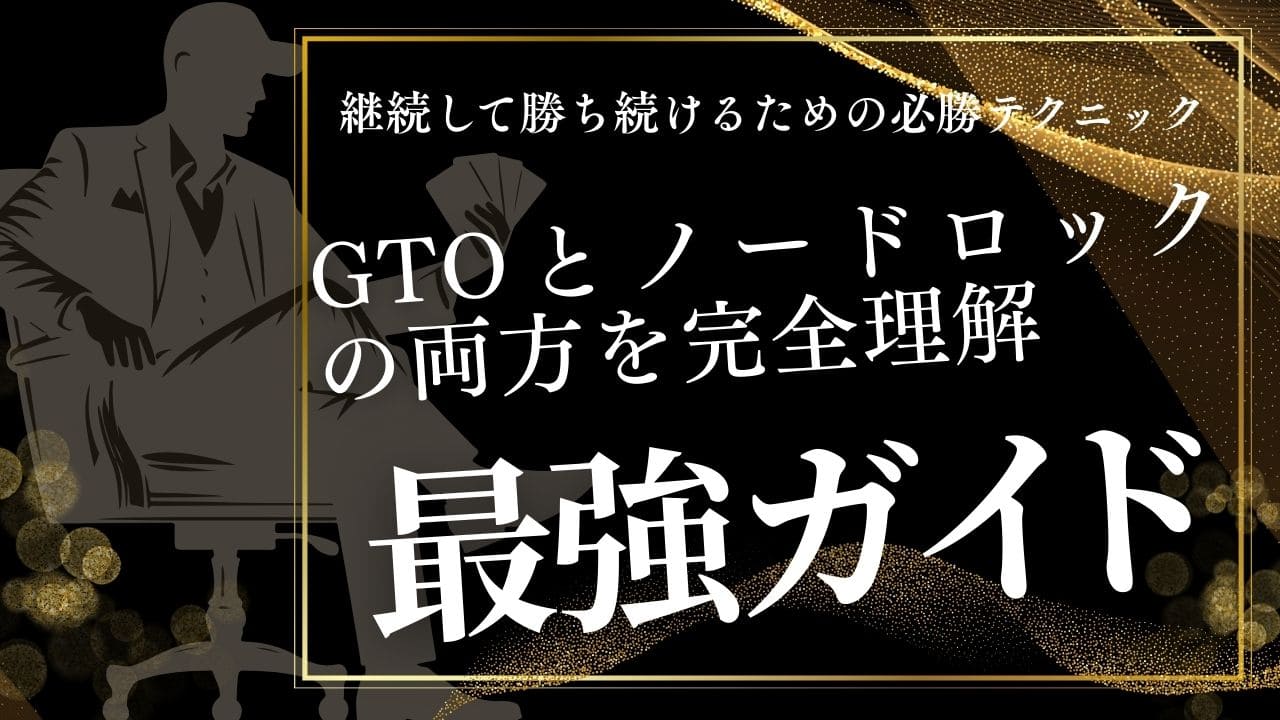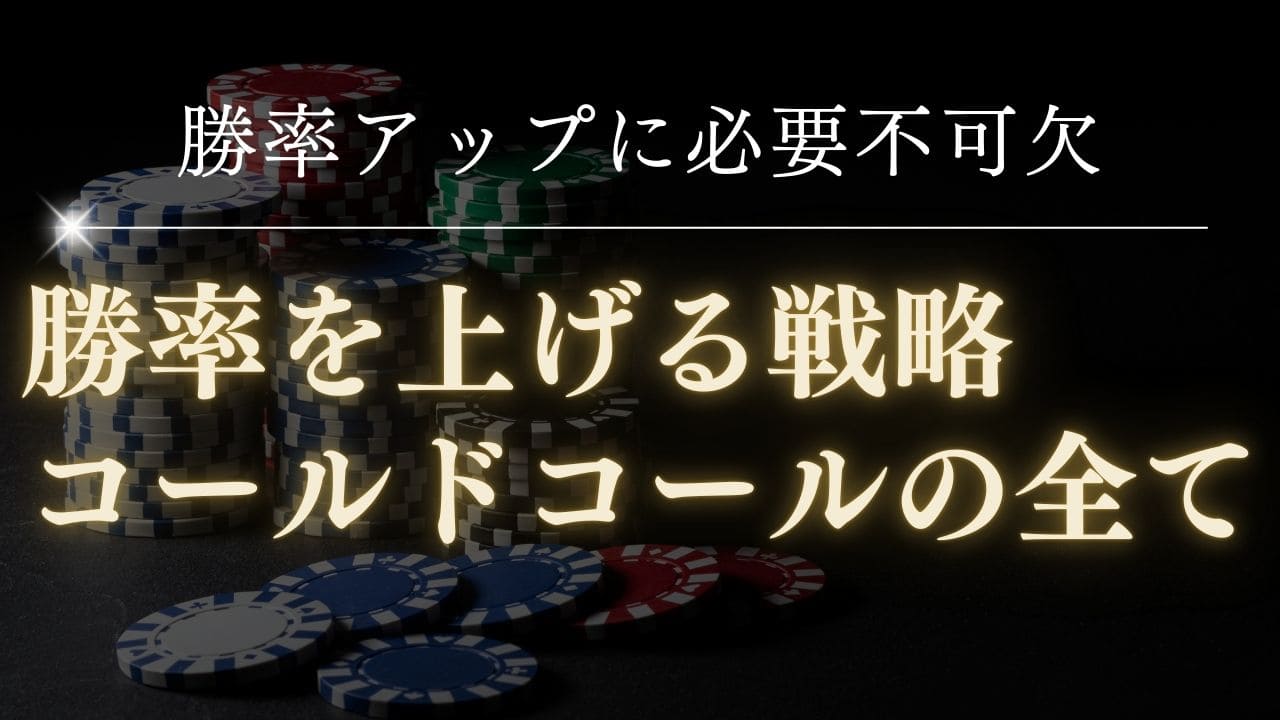【徹底解説】ポーカーのコールドコールとは?意味・メリット・デメリットと使い方ガイド
「コールドコール」とは簡単に説明すると、すでに誰かがレイズしている一方で、まだ自分はチップを入れておらず、同じレイズ額分のベットを行うことを言います。この「コールドコール」についてはプレイヤーによって様々な意見があり、本記事では、「コールドコール」の基本概念、メリット・デメリットなどを解説してまいります。
初心者にもわかりやすく説明しておりますので、ぜひ以下のより文章を読み進めていただければと思います。
1. コールドコールとは?

コールドコールの定義について
「コールドコール」とは、既に他のプレイヤーがベットやレイズをしている状況で、自分がまだチップを投入していない状態から初めてそのベットにコールする行為(つまり、レイズの同額のベットを行う)を言います。
たとえば、プリフロップ(各プレイヤーに2枚のカードが配られた状態)で最初のレイズがあった後、まだ自分が参加していない状態で、そのレイズに対して同額のチップを賭けることが「コールドコール」となります。
この行動に関してはいろんな議論が出ており、例えば「このままコールドコールするのは弱いハンドで参加してしまうリスクがある」
のから、むしろ強いハンドなら3ベット(再レイズ)すべきだと主張するプレイヤーもいれば、逆に、「自分の手が微妙な強さの場合、無理にレイズせずにリスクを抑えてフロップを見に行くためにコールドコールするのは戦略として有効だ」という主張もあります。
このように、コールドコールは相手の強さ、ポジション、そして自分のハンドの強さなど、複数の要因を慎重に考慮して判断すべきアクションとして、さまざまな視点から議論されています。
コールドコールの使用例
では、「コールドコール」はどういう場面で行われているかというと、
具体的には以下のような場面が想定されます。
- 複数のプレイヤーが既にベットしている場合:
最初のレイズに対し、さらに他のプレイヤーが参加しているとき、あなたが自分のハンドに自信があるがリスクは抑えたいときに使用されます。これにより、少ないリスクでフロップの展開を確認することができます。 - ハンドレンジが広い場合:
あなたの持つハンドが決してトップクラスではないものの、ポストフロップで相手の動向を見極めるために低コストでフロップを確認したいと判断した場合。
具体例としては、インサイドペア(例:6♥️6♣、7♦️7♠️、8♣️8♦️)やスーテッドコネクター(例:7♠️6♠️、9♥️8♥️、Q♦️J♦️)といった、完全に強いハンドではないが、ポストフロップで潜在的な強さを発揮できるハンドが挙げられます。
※インサイドペア:: 中程度(AAやKKなどのようなトップペアではない)の強さのペア
※スーテッドコネクター:同じマークが連続したカードの組み合わせ
2. コールドコールのメリット
フロップの展開を低リスクで確認
コールドコールの最大のメリットは、やはり低リスクでのフロップの状況を確認できる点です。フロップで自分のハンドが改善する可能性を低コストで探れることで長期的な勝率向上が期待できます。
相手のハンドレンジを絞りにくくする
相手に対して積極的にプレッシャーをかけずにコールすることで、対戦相手は自分のハンドレンジを狭めにくくなります。例えば、レイズや3ベット(再レイズ)の場合、相手は自分の手が強いと認識しやすくなります。一方で、「コールドコール」の場合、こちらの手札の情報を最小限に抑え、、柔軟なハンドレンジで戦える状態をキープできます。
ポジションを活かす戦略
特にインポジション(後ろからアクションする状況)にある場合、「コールドコール」はフロップ後のアクションで優位に立つことができます。なぜなら、ポジションが有利な場合、相手の出方を見てから自分の行動を決めることができるため、戦略的に優位に立てるからです。
3. コールドコールのデメリット
コールドコールのメリットについてこれまで紹介していきましたが、一方で、デメリットもあります。主なデメリットについて以下にまとめました。
フォールドエクテイの損失
「コールドコール」を選択してしまうと、相手をフォールドさせる機会を失うことになります。特に相手が強いハンドでレイズしてきた場合、もしそこで「コールドコール」をしてしまうと、ポットを大きくさせるリスクが高まり、結果として不利な状況に陥ることがあります。
※フォールドエクテイ:自分のベットやレイズに対して相手がフォールドする可能性
マージナルハンドでのリスク増大
勝つかどうか自信がないハンドでコールドコールすると、フロップ後の判断が難しくなり、最終的に勝率が低下するリスクがつきまといます。特に、弱いハンドで無理に参加すると、後々のベットやレイズに対して対応が遅れ、大量のチップを失う可能性があります。
※マージナルハンド:強いとも弱いとも言えない中間レベルの強さの手札
マルチウェイポットでの不利な状況
複数のプレイヤーが参加するマルチウェイポットでは、コールドコールによってポットが大きくなり、結果として不利な状況に陥りやすいです。相手の数が増えると、あなたの手配が相対的に強くない場合、負ける確率が高まり参加するハンドの選択がより重要になります。
マルチウェイポット:3人以上のプレイヤーがポットを争っている状況
4. コールドコールを使うべきシチュエーションについて
ポジションが有利な場合
「コールドコール」のメリットでも説明したように、インポジションにいる場合は、フロップ後に相手の行動を観察できるため、コールドコールを活用した際に優位にゲームを進めることができます。自分が他のプレイヤーがアクションしたのちに、行動できるという点を最大限に利用し、相手のプレイに応じて戦略を変えていくことが可能です。
※インポジション:他のプレイヤーのアクションの後にアクションできるポジション
相手が極端にアグレッシブな場合
対戦相手が頻繁にレイズやブラフを仕掛けてくる場合、「コールドコール」を選択することで相手の動向を見極めることができます。この場合、相手がブラフを仕掛けていることも多いため、適当なタイミングでコールドコールすることにより、不利な状況に陥るリスクを回避し、長期的に勝率を向上させることができます。
リスク管理をしながらフロップの展開を見たい時
強いハンドではなくても、フロップでハンドが改善する可能性があると感じだ場合、コールドコールは低リスクで情報収集ができる有効な戦略の一つです。この場合、参加金額を最小限に抑えることで、ポットの大きさをコントロールしながら、フロップ後の状況に応じて戦略を変更することができます。
5. コールドコールと他のアクションの比較
「3ベット」、「フォールド」との違い
「3ベット」のようにリレイズして、相手にプレッシャーをかけるのと違い、「コールドコール」は受身的な行為といえます。「3ベット」は強いハンドを持っているとアピールできる一方で、「コールドコール」は控えめであり、主な目的としては、フロップ確認のための手法と言えます。
また、「フォールド」はリスクを完全に回避するアクションですが、「コールドコール」はあくまでも参加し、フロップの動向を探る戦略であり、どの選択肢を選ぶのかが、勝率を上げる上で非常に重要となります。
※3ベット:誰かが行ったレイズ(ベット)に対して、追加でレイズ(リレイズ)をする行為
6. コールドコールを使用する際の注意点
コールドコールをする際にはいくつか気をつけるべき事項があります。
コールドコールについては、「フロップの展開を低リスクで確認したい場合」や、「相手のハンドレンジを絞りにくくしたい場合」などに有効ということについて説明をしましたが、使用する際には主に以下の点に注意する必要があります。
コールドコールの多用
コールドコールは低リスクでフロップの展開を確認できるという反面、コールドコールを多用しすぎると、対戦相手に自分のプレイスタイルが読まれやすくなるというリスクがあります。つまり、相手はあなたの手の強さや戦略が読まれ、結果的に長期的な勝率が低下する可能性があります。そのため、プレイする際には多用すると、コールドコールの効果が薄れてしまうということを常に頭に置いておく必要があります。
ハンドの強さとリスク管理
弱いハンドでコールドコールを行うと、フロップ後の判断が難しくなります。例えば、他のプレイヤーが強いカードを持ち、レイズをしてきた場合、どのように対応すべきか判断が困難になります。結果、勝率を下げる要因になりかねないため、自分のハンドの強さも考慮しコールドコールをすべきかを吟味する必要があります。
ポットオッズとのバランス
ポットオッズとは、現在のポットサイズに対して、コールするために必要な金額の割合を示す指標です。ポットオッズが不利な状況、つまり、コールするためのコストが高い場合は期待値が低くなります。すると、長期的な利益を得ることが難しくなります。そのため、コールドコールを行う際には、ポットオッズを考慮し、そのオッズに見合ったリターンが期待できるかを判断していかなくてはなりません。
※ポッドサイズ:プレイヤーがベットまたはレイズしたチップの総額
7. よくある質問(FAQ)

コールドコールを成功させるためのポイントは?
・ハンドレンジの見極め: 自分のハンドがフロップで改善する可能性があるかを冷静に判断する。
・ポジションの有利さ: 後ろでアクションできる場合は、コールドコールが効果的。
・相手の傾向の把握: アグレッシブな相手には慎重に対応し、相手のブラフを見抜く力が必要となります。
オンラインとライブポーカーでの違いは?
オンラインポーカーでは、データや統計情報をもとに冷静に判断できるため、コールドコールも効率よく使える傾向にあります。一方で、ライブポーカーでは相手の表情や態度、テーブルマナーなども影響するため、コールドコールのタイミングやリスク管理などが難しいと言えます。
トーナメントとキャッシュゲームでの違いは?
まず、トーナメントは状況によってチップの価値の変動することやスタックが短いなどを考慮する、「コールドコール」で無駄にチップを損失するなどしてしまうことは致命的な状況を引き起こす可能性があります。そのため、慎重なリスク管理が求められ、「コールドコール」を選択する際には慎重にプレイしていく必要があります。一方で、キャッシュゲームはスタックが深く、「コールドコール」でのチップの全体の占める割合が小さいこともあり、フロップの動向判断の手段として低コストでできる点で有効となります。もちろん、状況に応じて「コールドコール」をするかどうか判断していく必要はありますが、戦略を状況に応じて変えられるという点で有利な手段と考えられます。
8. まとめ

本記事では、「コールドコール」の定義から、具体的な使用シチュエーションまで詳しく解説してまいりました。一概に「この状況ではこうすべき」と断言することは難しく、常に自分のプレイスタイルや戦略に合わせて使い方を考えることが重要です。
コールドコールの判断基準
・ポジション: 自分が後ろのポジションにいる場合、他のプレイヤーのアクションを確認してから自分の判断を下せるため、コールドコールを選択することにより優位な状況に立てることができます。
・ハンドの強さ: 自分が絶対的な強いカードを持っていない場合でも、ポストフロップの展開が期待できると判断した際には、コールドコールすることで低リスクでゲームに参加することができます。
ぜひ本記事に内容を参考にしながら、実際にプレイしてみて自分のスタイルに合ったコールドコールの使い方を見つけていただければと思います。
また、ポーカーの記事についてはこちらにまとめておりますので、よろしければ以下のリンクから確認してみてください。