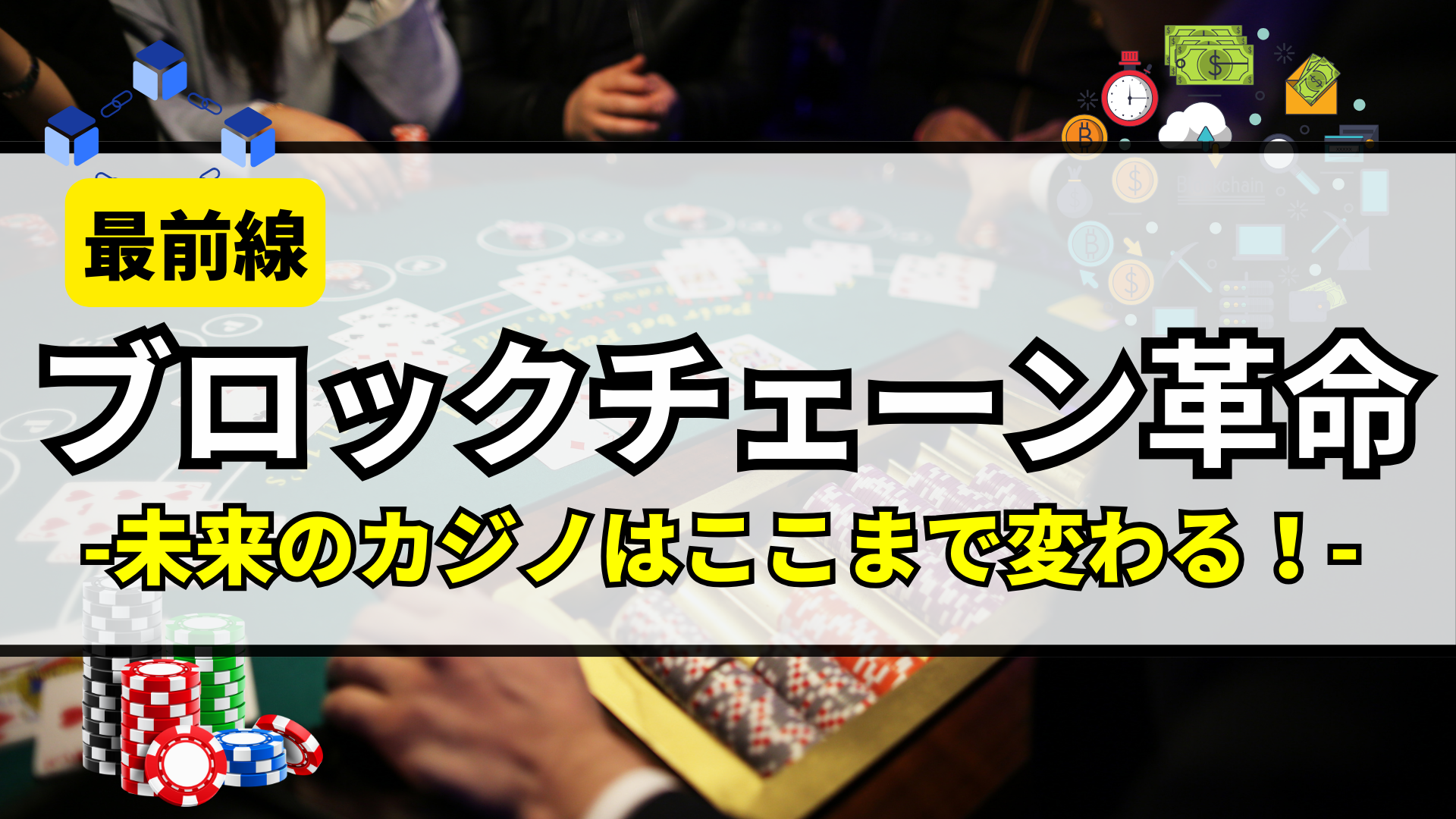仮想通貨初心者が必ず経験する『失敗あるある』15選
今回の記事では、仮想通貨を始めたばかりの初心者がついやってしまいがちな失敗例を15個にまとめてご紹介します。
仮想通貨はとても便利な一方で、正しい知識がないと大きなリスクを伴うこともあるため、ぜひこの記事を読みながら、自分にも当てはまるところがないかチェックしてみてください。
初心者の失敗①:
急な暴落で焦って即売り 、 翌日価格が戻る
よくあるシナリオ
①仮想通貨のニュースで「ビットコイン暴落中!」、「○○コイン、20%急落」などを見る
↓
②保有していた通貨の価格が10〜30%下落し、「このままゼロになるかも…」とパニックに
↓
③慌てて全額売却
↓
④翌日、市場が落ち着いて価格がV字回復
↓
⑤「売らなきゃ良かった…」と後悔
なぜ、このような行動をしてしまうのか?
【1】感情による判断(パニック売り)
- 人は「損をしたくない」心理(損失回避バイアス)が強いため、下落相場では「早く逃げなきゃ」という焦りが勝る
- たとえ一時的な下落でも、「今売らないと全部失う」などの思い込み
【2】経験不足による「調整」の誤解
- 仮想通貨は価格変動が大きい市場
- 1日に10%以上動くのは珍しくない
一方で、「10%下がった=終わり」と捉えてしまい、冷静な判断ができなくなる
対策①:価格変動に慣れる
- 仮想通貨は「一時的に下がることがある」ことが日常的に起こりうる
- チャートを毎日見ながら、肌感覚で理解する経験を積む
対策②:「自分ルール」を明文化する
以下のようなルールを紙に書いておく or スプレッドシートで管理
| 状況 | 自分のルール |
|---|---|
| 購入後10%以上下がったとき | 売らない。最低1週間は様子を見る |
| ニュースで悪材料が出たとき | 一晩置いてから判断する。 |
| 利益が10%出たとき | 利益確定する or 半分だけ売る |
対策③:長期的視点(ガチホの基本)
- 仮想通貨は「短期で10%下落しても、半年後には3倍」などの極端な例が多い
- 数時間〜数日で判断しない、1ヶ月〜1年単位で見る視点を持つ
- 本当に価値がある通貨なら、時間が味方となる
・基本として「焦って動かない仕組み」を作る。
・感情ではなくルールで動くことで、長期的には勝てるようになる
失敗例②:
送金アドレスを間違えて資金を損失
よくあるミス:送金アドレスの1文字ミスで全額失う
仮想通貨の世界では、送金ミスは取り返しがつかなくなります。
銀行振込用な口座番号が間違ってしまっても戻ってくるなどのようなシステムはありません。
ブロックチェーンは「誰が・どこに・いくら送ったか」が改ざんできない一方で、一度送ったトランザクションは取り消せないという特徴があります。
実例1:コピー&ペーストしたはずが。。。
- アドレスの前後に空白や改行が入っていた
- スマホでコピペしたら、別の行まで選択していた
- QRコードの読み取りミスで別の文字列になっていた
実例2:手入力による操作ミス
- アルファベットの「O」と数字の「0」、「l(エル)」と「1」の打ち間違い
- そのまま打ち間違いに気づかずに送金実行
実例3:ブロックチェーンの勘違い
・Ethereum(ERC-20)アドレスとBinance Smart Chain(BEP-20)アドレスを勘違い
→ ネットワークが異なり、資金を消失
送金ミスは自己責任でサポートなどが通用しない
・多くのウォレットや取引所は、送金ミスに対して返金サポート対応は不可。
・「仮想通貨を送る前に確認することがユーザーの責任」というのが仮想通貨の基本スタンス。
対策:“慎重すぎる”くらいの確認を
1. アドレスは絶対に手入力しない
→ 必ずコピペ or QRコードを使用。手入力はヒューマンエラーの元。
2. コピペ後、目視で“頭3文字”と“末尾3文字”を確認
→ 例:0xA3F...D9c のように「頭」と「尻」だけでも照合する習慣をつける。
3. まず少額でテスト送金
→ 大きな金額を送る前に、まずは100円程度の少額を送ってみて、正しく届くか確認。
4. チェーン(ネットワーク)を再確認
→ 取引所やウォレットで送信前にERC-20かBEP-20かなどのチェーン選択を間違えていないかチェック。
5. 定期的に自分のウォレットとアドレス帳を整理
→ 一度使ったアドレスを「お気に入り」や「アドレス帳」に登録し、再入力の手間が省け、ミスも減少。
| 内容 | 結果 |
|---|---|
| アドレス1文字ミス | 資金の損失 |
| ネットワークミス | 資金が届かない/永久ロックの可能性あり |
| コピー&ペーストの注意 | 改行や空白が混じる可能性あり |
| 対策 | 少額送金 → アドレス目視確認 → ネットワークチェック |
【誤送金対策】
送金前にアドレスを2回以上チェック。テスト送金で少額を先に送るなども効果的。
失敗例③:
SNSの「爆上げ予想」に乗って大損
よくあるシチュエーション
- X(旧Twitter)やYouTubeで「100倍確定コイン!」「今が買い時!」 などの投稿を目にする
- 「今買えば数ヶ月後には億り人!?」という煽り文句を鵜呑みにする
- 少しでも乗り遅れたくなくて、内容をよく調べずに買ってしまう
- 数日後、価格は下落し、元本の半分以下になる
このような投稿が拡散される理由
1. インフルエンサーが仕込んでから煽る
- 多くの場合、投稿者は事前に安く買って仕込んでから投稿している
- その後フォロワーに買わせて価格を釣り上げ、自分だけ高値で売り抜く
(ポンプ&ダンプ手法)
2. アルゴリズムで“煽り系”がバズりやすい
- SNSの仕組み上、「爆上げ」「今すぐ買え」などのタイトルは拡散されやすい
- 数字が入った煽り(「100倍確定」など)は視聴者の関心を引きやすい
3. 詐欺コインやスキャム案件も多数
- 「〇〇コインが上がる!」と紹介しつつ、実際はプロジェクト自体が実体のないという可能性もある
- トークンを買ったら最後、売却もできず資金がロックされることも
初心者が信じてしまう理由
| 心理 | 解説 |
| FOMO(取り残される恐怖) | 「今買わないと損するかも!」という焦り |
| “億り人”への憧れ | SNSで「10万円が1億になった」体験談に影響を受ける |
| 根拠があるように見える | チャートや専門用語が並び、本当のように見える |
対策①:SNSの情報は「エンタメ」として見る
- SNS投稿のほとんどは「根拠のない煽り」 や 「宣伝」
- 情報の出所が不明確なものはすぐに飛びつかず、「面白いけど、すぐには信じない」という冷静なスタンスを持つべき。
対策②:必ず「一次情報」に立ち返る
チェックすべき一次情報:
- プロジェクトのホワイトペーパー(=公式資料)
- チームメンバーの実績・過去のプロジェクト
- トークンの発行枚数や配布比率
対策③:過去の詐欺例を知る
実例:典型的なポンプ&ダンプ型スキャム
- 2021年:「SaveTheKidsトークン」事件
→ 有名YouTuberたちが宣伝 → 一気に高騰 → 彼らが売り抜け → 一般投資家が大損
上記のように、仮想通貨では
影響力ある人が紹介=安全ではない可能性があります。
対策④:買う前に最低1日は考え直す時間を設ける
- 気になる通貨があっても、すぐには買わず「翌日まで寝かせる」ことが有効
- 熱が冷めた時に再度見直すことで感情に流されにくくなる
対策:
SNS情報はあくまで参考程度に。
公式情報やホワイトペーパーなど、一次情報を重視することが大切。
失敗例④:
レバレッジ取引で大きく負ける
レバレッジ取引とは?
レバレッジ(leverage)とは、「てこの原理」のことを意味しており
手持ちの資金よりも大きな額の取引をすることを指します。
例:10倍レバレッジの場合
- 所持金:1万円
- 実際に動かす取引額:10万円分(1万円 × 10倍)
- 価格が10%下落しただけで、元本すべて失う
初心者がやってしまう心理
| 心理 | 内容 |
| 一発逆転願望 | 少ない元手で大きく増やしたい。「3万円を一気に30万に」 |
| 成功者の体験談に影響を受ける | 「レバ10倍で100万儲けた」などの投稿に影響される |
| 損切りの判断ができない | 想定外の方向に動いても「戻るはず」と考える |
なぜ初心者にレバレッジは危険な理由
1. 損失スピードが異様に早い
- レバレッジ10倍以上の場合、1割の下落で即ロスカット
- チャートを見ている間にゼロになることもザラにある
2. 感情が先に動き、冷静な判断ができない
- 「あともう少しで戻る」など非合理な判断に陥る
3. 手数料・スリッページで実際はもっと損する
- 仮想通貨取引所の清算手数料・資金調達コスト・スプレッドが含まれると、理論以上に負けやすくなる
対策①:レバレッジの破壊力を理解する
レバレッジ別ロスカットライン(参考)
| レバレッジ倍率 | 必要な逆行幅で資産ゼロになる |
| 2倍 | -50% |
| 5倍 | -20% |
| 10倍 | -10% |
| 20倍 | -5% |
対策②:初心者は「現物取引」から
- レバレッジなしの現物取引では、資産がゼロになることはない
- 価格が下がっても保有し続けられるため、感情に左右されにくい
対策③:デモ取引 or 少額からスタート
- バイビットやビットフライヤーなどの取引所にはデモトレードもある
- 実際に始める場合も「1,000円程度の少額」から始めることがオススメ
対策④:「損切りルール」を事前に決める
- 「含み損10%になったら損切りする」などの自分ルールを設定する
- あらかじめロスカットのラインを決めておき、自動損切り設定を使うなど
| ポイント | 内容 |
| レバレッジは破壊力が大きい | 逆に動いたら一瞬でゼロのリスクも |
| 初心者は感情で判断しがちになる | 経験なしでハイリスクを取ると危険 |
対策:
レバレッジ取引は上級者向けであり、まず初心者は現物取引で経験を積むことが重要。
失敗例⑤:
草コインに投資して資産がゼロに。。。
「草コイン」とは?
- 草コインとは、時価総額が低く、知名度のないマイナーな仮想通貨の俗称です。
- 特徴として価格が数銭〜数十銭と極端に安く、「100倍」「1000倍」といった一攫千金の可能性があります。
よくあるパターン
- SNSで「このコイン、〇〇倍確定らしい」と話題に
↓ - 実際に価格が急騰し、購入
↓ - 数時間後に急落
↓ - チャートはほぼ動かず、そのまま価格がゼロに
なぜ初心者は草コインを購入してしまうのか?
| 心理 | 内容 |
|---|---|
| 夢がある | 一攫千金を追ってしまう |
| SNSで話題 | 草コイン専門アカウントやYouTuberが「爆上げ」などの煽りを受ける |
| 少額で始められる | 1000円で何万枚も買える |
| 実態を調べずに買ってしまう | 安い=お得、と誤解する |
草コイン投資の危険性
1. 開発が途中で止まる
例:GitHubや公式サイトが放置、SNS更新なし
→ 実質「プロジェクト終了」
2. 売ることすらできない
- 草コインの多くは、DEX(分散型取引所)でしか売買できない
- LP(流動性提供)が消えると、買う人も売る人もいなくなり、実質ロック状態に陥る
3. トークン設計自体が詐欺
- 初期保有者(開発側)が9割以上を保有 → 価格が上がった瞬間に一気に売り抜け(ラグプル)
対策①:草コインは「遊び枠」だと割り切る
- 草コインに投資するなら、「失ってもいい金額だけ」
- 例:投資金の1〜5%程度に抑える
→ 本気で稼ぐつもりではなく、ギャンブル・宝くじ感覚で
対策②:「実績ある通貨」に集中
- ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)、ポリゴン(MATIC)など
- 時価総額上位で数年の運用実績がある通貨は、一定の信頼性あり
対策③:買う前にプロジェクトを必ずチェック
チェックポイント:
| 項目 | 確認方法 |
|---|---|
| ホワイトペーパー | ちゃんと存在するか、中身は具体的か、など |
| 開発状況 | GitHubの更新状況、アプリや製品のリリース進捗 |
| チームの実在性 | 顔・名前・過去の実績が公開されているか否か |
| 取引所の上場状況 | 信頼できる取引所に上場しているかどうか |
| トークン配布比率 | チーム・初期投資家が大半を保有していないか |
対策④:価格より「中身」を確認
- 価格が0.01円だからといって「安い」とは限らない
→ 実際には発行枚数が数兆枚あり、上がる見込みがないケースもある
対策:
草コインは現実、99%が消えるプロジェクト。まずは実績のある通貨から始めること。
自分で調べ、自分で納得して投資する姿勢がなにより重要であり、プロジェクトの公式サイトや開発状況も必ず確認する。
失敗例⑥:
セキュリティ設定が甘くてハッキング被害
典型的な失敗例
- パスワードを「123456」などのような推測しやすい文字列に設定
- スマホのSMSを使った二段階認証(2FA)だけを設定
→ SIMスワップで突破される可能性あり
なぜ仮想通貨初心者はハッカーに狙われるのか?
| 理由 | 説明 |
| 資産は完全自己管理 | 銀行のような保証や凍結機能がなく、 盗まれたら基本「戻らない」 |
| 仮想通貨取引所のセキュリティに依存 | 自分で対策していない人が多い |
| SNSやメールの情報から推測されやすい | 同じIDやパスワードを使い回している人が多い |
実際のハッキング手口
1. ブルートフォース攻撃(総当たり)
- 短くて単純なパスワードは、数分〜数時間で突破される
2. フィッシング詐欺
- 偽物の取引所サイトに誘導
→ メールアドレスとパスワードを入力
→ 乗っ取られる
3. SIMスワップ(SMS認証の危険)
- 携帯キャリアのサポートを騙して他人のSIM情報を奪取
→ SMS経由の2FAを突破されてしまう
被害後の現実
- 仮想通貨は送金履歴がブロックチェーンに残るが、誰が受け取ったかは分からない
- 返金・追跡・補償は基本的に一切なし
- 取引所や運営も、「ユーザー側の設定ミス・流出」と判断されれば、補償対象外
具体的な対策
1. 強力なパスワードを使う
- 英数字+記号を含む 12文字以上(理想は20文字)
例:x@P7#lK2z!vR9T$gW1 - パスワードマネージャーの活用
2. 二段階認証(2FA)は必須
- SMS認証よるGoogle AuthenticatorやAuthyなどのアプリを使用
- 取引所、ウォレット、メール、パスワードマネージャーに適用
3. 重要な資産は「ハードウェアウォレット」
- インターネットから完全に切り離されたオフライン保管(コールドウォレット)
例:Ledger Nano X、Trezor
<メリット>
・オンライン攻撃から完全に守れる
・「PINコード」&「リカバリーフレーズ」で復元可能
4. 取引所は「信頼性と保険のあるところ」を選択
- 世界的にセキュリティ評価の高い取引所(例:Binance、bitFlyerなど)を利用
- 運営実績やマルチシグ・保険・補償制度の有無も確認
5. SNS連携やログインは極力避ける
- 「Googleログイン」「Apple IDログイン」など便利な反面、第三者に依存するリスクもあり
- 「メールアドレス」+「強固なパスワード」+「二段階認証(2FA)」が最も堅実
| セキュリティ弱点 | 被害内容 |
| 短いパスワード | 総当たりで突破される可能性あり |
| 2FA未設定 or SMSのみ | SIMスワップで突破される可能性あり |
| PCやスマホの感染 | マルウェアで秘密鍵流出の可能性あり |
| オンラインウォレットのみ | ハッキングで全資産奪われる可能性あり |
対策:
二段階認証は必須。
重要な資産はハードウェアウォレットに保管。
失敗例⑦:
高値づかみしてしまう
人は高値づかみの原因
1. FOMO(Fear of Missing Out)= 取り残される恐怖
- 「この流れに乗らなければ、もうチャンスはない」と錯覚
→実際は価格は常に波を打って動いているため、焦る必要はない
2.「今が一番安全に思える」という錯覚
- 価格が上がっている=好調=安心、という心理が働く
→ しかし、価格が上がりきったところこそ最も不安定
3. 人は「結果」を見て判断しがち
- 過去の上昇を見て「まだ伸びる」と期待
→ チャートの“過去の栄光”に投資してしまう
その後の“塩漬け地獄”
一度買った価格を超えるまで何ヶ月も待つ
↓
他の通貨に資金を移せず、身動きが取れない状態
↓
やっと上がった時にも「また上がるかも」と考え売る決断ができず、再び下落
対策①:「急騰=買い時」とは限らないと理解
仮想通貨市場は非常にボラティリティ(変動性)が高く、価格は必ず上下に波を打ちます。
そのため、「今上がっているからといって、今後も上がる」とは限りません。
| 状況 | 買うべきか? |
| 急騰して数時間で+20% | ×買い控え or 小額だけ |
| 一時調整後に再び上昇 | △ 注意深く判断 |
| 横ばい or 軽い押し目形成 | ◎ 分散買いのチャンス |
対策②:ドルコスト平均法(DCA)を活用する
ドルコスト平均法とは?
定期的に一定額ずつ買っていく手法。
価格が高い時には少量、価格が安い時には多く買うことになり、購入単価が平準化される。
例:
- 毎週1万円ずつ、ビットコインを買う
→ 高値でも買うが、安値でも買うため、一発で高値づかみするリスクが大幅に減る
DCAのメリット
| 項目 | 内容 |
| 感情に左右されない | 「今が買い時か?」を悩まなくて済む |
| リスク分散 | 高値で買っても、後で安値で買えば平均化される |
| 長期投資に向いている | 上下を繰り返しながら上昇する仮想通貨と相性が良い |
対策③:「買う理由」が説明できるかを自問
「今買いたい」と思った時、“なぜ今なのか”を自分で言語化できるか?
- 「価格が上がっているから」だけで買うのは危険
- 自分なりのルール(チャート分析・ニュース・材料など)で納得したタイミングで買うのが安全
テクニカルに避ける方法
- RSI(相対力指数)70以上:買われすぎサイン
→ 買いを控える - 急騰後の長いヒゲ付き陰線:反転の合図になりやすい
- サポートライン・レジスタンスラインを見て、「反発が弱い=上昇終了」の可能性を考慮
| ポイント | 内容 |
| 高騰している=安全ではない | むしろ「天井」であることが多い |
| 感情に流されて買うと高値づかみしやすい | FOMOは最大の敵 |
対策:
価格が急騰している時こそ冷静に。
買い時を分散(ドルコスト平均法)が有効。
失敗例⑧:
利益確定のタイミングを逃す
よくある失敗シナリオ
- 投資した通貨が思いのほか上昇して+50%、+100%の含み益になる
- 「まだ上がるはず!」「ここで売ったらもったいない」と利確を先延ばし
- 数日後、大口の利確・ネガティブニュースで急落
- 結局マイナス、または買値まで戻って「利確のチャンスを逃した…」と後悔
利益は「確定して初めて利益」
仮想通貨は含み益(まだ売っていない利益)が発生しやすいですが、それは“絵に描いた餅”にすぎません。
チャートの上下で一喜一憂するだけで、最終的に利確できなければ意味がないです。
利確できない心理
| 心理 | 内容 |
| もっと上がるはず | 「今売ったらもっと上がって後悔するかも」 |
| 過去の暴騰と比較してしまう | 「あの時は10倍になったし、今回もいけるかも」 |
| 売ったら終わり=寂しさ | 売ってしまうと上がっても恩恵がない → 謎の未練 |
よくある後悔パターン
- 「+80%で売っておけば…」→ 結局-10%に転落
- 「一部だけでも利確しておけばよかった」となるケースが非常に多い
- 「倍になったら売る」と思っていたのに、具体的に売る価格を決めていなかった
対策①:“売る基準”を事前に決めておく
例:目標利益率で利確するルール
| 利益率 | アクション |
| +30% | 元本の30%を利確する |
| +50% | 元本の50%を利確する |
| +100% | 元本全額+利益の一部を利確 |
→ 「段階的な利確ルール」を事前に作っておくことで、感情に流されずに売却できる
対策②:指値注文やトレーリングストップを活用する
指値注文(Limit Order)
- 「この価格まで上がったら売る」と決めておける
- 例:現在価格が¥8,000 → ¥10,000で売却注文を事前に設定
トレーリングストップ(対応取引所限定)
- 価格が上がるにつれて売りラインが自動的に引き上がる
→ 急落に巻き込まれず、利益を守りつつ最大化
対策③:「一部売却」という選択肢を持つ
- 全額を売るか保有するか、“オール or ナッシング”の思考は危険
- たとえば:利益が+50%なら「半分利確して、半分ホールド」など柔軟な選択ができると◎
対策④:「売ったあとに上がる」ことを受け入れる
- 利確後に価格がさらに上がることは、ほぼ確実に起きます
- でもそれは「想定外のボーナス」なので、悔やむ必要はないです
- 利益が確定したなら、それが正解の行動です
| ポイント | 内容 |
| 利益は「確定」して初めて意味がある | 含み益は幻 |
| 欲に飲まれると利確を逃す | 感情管理が必須 |
| 対策 | 目標利益率の事前設定/段階的利確/指値注文/一部売却 |
対策:目標利益率を設定し、自動売却(指値注文)を活用するのも有効。
失敗例⑨:
ギャンブル投資に走る
なぜギャンブル投資に陥るのか?
| 心理 | 内容 |
| 一発逆転願望 | 少ない元手で「大金持ち」になりたいという気持ち |
| 他人の成功体験に影響される | 「たった3日で5倍」などの誇張された体験談に刺激される |
| 分析よりノリ・雰囲気重視 | プロジェクト内容や価格チャートは見ない/見ても理解していない |
| 負けを取り戻したい | 一度損をすると「取り返そう」と無謀な投資額に手を出す |
ギャンブルと投資の違い
| 項目 | ギャンブル型 | 投資型 |
| 根拠 | 勘、ノリ、他人の意見 | 分析・リサーチ・ロジック |
| 資金配分 | 一点張り | 分散・リスクコントロール |
| タイミング | 運まかせ | 計画的・戦略的 |
| 意識 | 「当たれば勝ち」 | 「負けを避けながら増やす」 |
| 再現性 | なし | あり(学習・改善が可能) |
実際に起こる悲劇
- わけも分からず話題の草コインに10万円突っ込む
→ 3日後に98%下落 - SNSで「大口が買ってる」と見て買ったら、実際はポンプ&ダンプだった
- 一時的に増えても、次に欲張って全部溶かす
→ 利益が出ても長続きしない
脱・ギャンブル投資への具体的なステップ
1. 投資目的を言語化する
「なぜ仮想通貨に投資するのか?」をノートやスマホメモに書き出す。
・長期資産形成のため?
・毎月数%の安定収益を狙いたい?
・Web3・新技術に参加したい?
→ 目的が明確になると、「その投資は目的に合ってるか?」を判断できるようになる。
2. 自分ルールをつくる(最重要)
以下のようなシンプルなルールからでもOK:
| 項目 | ルール例 |
| 投資額 | 1銘柄あたり資産の10%まで |
| 銘柄選び | ホワイトペーパーが公開されていて、実働中のプロジェクトのみ |
| 利確ライン | 20%で半分利確、50%で残り利確 |
| 損切りライン | 購入価格から15%下落したら売却 |
3. 投資前に「3チェック」する
- そのコインは何を解決するプロジェクトなのか?
- 時価総額と流通量は健全か?
- チャートは明らかに天井 or 底ではないか?
→ この3点を事前にチェックするだけで、投資の成功率は大きく変わります。
4. 小さな勝ちを積み上げる感覚を身につける
- 「2倍になったら全部売る」はギャンブル脳
- 10%でも利益が出たら少しずつ確定して、資産を守る習慣をつける
- 「一発で資産倍増」よりも「年利20〜30%で増やす」のほうが再現性があり、安定
| 項目 | 内容 |
| ギャンブル投資とは? | 根拠のない全力投資、感情優先のトレード |
| なぜ起こる? | 欲望・焦り・SNSの影響 |
| 対策 | 自分ルール・目的設定・分散・利益管理 |
対策:仮想通貨投資は計画性と分析が重要。ギャンブルと投資の違いを明確に意識する。
失敗例 10:
手数料の存在を忘れて損する
よくある失敗パターン
- 「上がったらすぐ売る、下がったらすぐ乗り換え」を繰り返すうちに…
→ いつの間にか資産が目減りしている
→ 原因は【手数料】だった
仮想通貨にかかる主な手数料の種類
| 手数料の種類 | 内容 | 具体例 |
| 取引手数料 | 取引所での売買時に発生 | Binance:0.1%、bitFlyer:0.01〜0.15% など |
| スプレッド | 買値と売値の差。事実上の手数料 | 日本の販売所はスプレッドが大きい(3〜5%もあり) |
| 送金手数料(ガス代) | ブロックチェーンで送金する際の手数料 | Ethereumの送金:混雑時で1,000円以上になることも |
| 出金手数料 | 取引所から銀行・ウォレットへ出金する際に発生 | bitFlyer→銀行:330円/BTC出金:0.0004 BTC など |
ありがちな「見えない損」
ケース①:販売所で頻繁に売買 → スプレッドで損
- BTCを販売所で買う → 実際の市場価格より3〜5%割高
- すぐ売る → また3〜5%引かれる
→ 合計で10%近く損失
ケース②:NFTを複数購入 → イーサリアムのガス代だけで数千円消える
- 1件ごとに300〜2,000円程度のガス代
- 結局、NFTよりも手数料のほうが高くつくことも
ケース③:海外取引所間で頻繁に資金移動 → 毎回の送金で資産減少
- 仮想通貨はネットワークごとに手数料が異なる
- ERC-20(イーサリアム)上の送金はとにかく高額になりがち
対策①:手数料込みで損益を計算するクセをつける
仮想通貨を買うとき・売るときは**「どれだけ利益が出たか?」ではなく「手数料差し引いて残る額は?」**を確認。
| 購入価格 | 売却価格 | スプレッド+手数料 | 実際の利益 |
| ¥10,000 | ¥10,500 | 約5%(¥500) | ±0円(実質利益ゼロ) |
対策②:「取引所」と「販売所」の違いを理解する
- 販売所(簡単取引):初心者向けだがスプレッドが大きく損しやすい
- 取引所(板取引):少し難しいが、取引手数料が圧倒的に安い
→ 取引に慣れてきたら、板取引を優先的に使うようにしよう
対策③:送金時は「ネットワーク選択」に注意
- ETH(ERC-20):ガス代が高騰しやすい(混雑時で数千円)
- BSC(BEP-20)やPolygon:比較的安価(数十円〜数百円)
→ 送金先が対応していれば、手数料の安いネットワークを選ぶだけで節約効果大
対策④:売買頻度を減らす=コスト節約になる
- 「毎日のように売買」=そのたびに手数料が発生
- 特に初心者は、ポジションを持ったらある程度放置できるくらいの期間設計をするのがおすすめ
→ 自然と手数料負けを避けられる
| 注意点 | 内容 |
| 手数料は見えにくいが確実に減る | 取引所手数料、スプレッド、送金料などが積み重なる |
| 頻繁な売買は危険 | 利益が手数料に食われやすくなる |
| 対策 | 手数料を事前に計算/販売所は避ける/安いネットワークを選ぶ/回数を絞る |
対策:取引時には必ず手数料を確認。頻繁な売買は控えるのも一つの手です。
失敗例 11:
税金に関する知識不足で確定申告に失敗
こんなミスがよくある
- 仮想通貨の売却益を出したが「申告しなくていいと思っていた」
- NFTを転売して利益が出たが「課税対象とは知らなかった」
- 損失もあったから「トータルでマイナス」と自己判断し、申告を忘れる
- 数年後に税務署から連絡 → 数十万円〜数百万円の追徴課税+延滞税
仮想通貨に関する税金の基本知識
| 項目 | 内容 |
| 課税対象 | 仮想通貨の売却益、他の仮想通貨との交換、商品購入、NFT売買など |
| 所得区分 | 日本では基本的に「雑所得」扱い(総合課税) |
| 税率 | 所得金額に応じて 5〜45%+住民税10%(最大55%) |
| 申告義務 | 年間の仮想通貨利益が 20万円を超えた場合(会社員)に確定申告が必要 |
「課税されるのは円に換金した時だけ」と思っていませんか?
実は以下のようなケースでもすべて課税対象となります:
課税されるタイミングの例:
| ケース | 説明 |
| BTC→ETHに交換した | 日本円に換金していなくても、**“利益確定”**とみなされ課税対象 |
| コインで商品を購入した | 実質的な“売却”と見なされる |
| エアドロップやマイニング | 原則として受け取った時点で課税される |
よくあるトラブル事例
【ケース①】
3年前に仮想通貨を売って申告せず → 国税庁から無申告加算税+延滞税の請求
【ケース②】
海外取引所で取引していたため、「バレないだろう」と申告しなかった → 数年後、銀行への送金記録から発覚
【ケース③】
損益の記録を取っておらず、「いくら儲かったのか分からない」 → 税理士も対応困難に
対策①:すべての取引履歴を保存する
- 利用している取引所から「年間取引レポート」や「CSVデータ」をダウンロード
- 海外取引所やDeFiでの取引も忘れずに記録
- できれば**仮想通貨損益計算ソフト(Cryptact、Gtaxなど)**を利用すると管理が楽
対策②:税金の知識を最低限持っておく
| 覚えておきたいポイント | 解説 |
| 雑所得で申告 | 仮想通貨利益は基本「雑所得」。損益通算不可なので注意 |
| 利益は「売った時点」で確定 | 他通貨への交換や決済でも「確定扱い」になる |
| 経費は一部認められる | 取引所手数料・ハードウェアウォレット購入などは必要経費として計上可(条件あり) |
対策③:確定申告前に税理士か税務署に相談する
- 仮想通貨に詳しい税理士は徐々に増えている
- 国税庁のWebサイトにも「仮想通貨に関する申告ガイド」がある
→ 迷ったら自己判断せずに専門家へ
対策④:利益が出たら“税金分を取り分けておく”
- 仮想通貨で20万円以上の利益が出た場合、確定申告と納税は翌年春にまとめてやってくる
- 急に税金を支払えなくなるリスクを避けるために、
→ 利益が出たらその都度、税金分(30〜50%)を別口座に取り分けておくのが安心
| 項目 | 内容 |
| 申告しないとバレない? | バレます。特に銀行・取引所経由の送金履歴で |
| どこまでが課税対象? | 円に換金・他通貨への交換・決済など、全部対象 |
| 対策 | 取引履歴の保存/損益計算ツールの活用/税理士相談/税金分の確保 |
対策:取引履歴を記録し、税務署や専門家に早めに相談するのが安心。
失敗例12:
ウォレットのパスワードを紛失する
「パスワードを失う」と何が起きるのか?
仮想通貨ウォレットは、基本的に自分自身が銀行代わりです。
ログインパスワードや「秘密鍵」「シードフレーズ(リカバリーフレーズ)」を紛失した場合、基本的に復旧や補償は受けられません。
よくある紛失・アクセス不能のパターン
| ケース | 結果 |
| 紙に書いたパスワードをなくす | ログインできず、資産にアクセス不可 |
| スマホが壊れてウォレットアプリごと消えた | リカバリーフレーズがないと復元不可能 |
| メモ帳に保存していたがPCごと故障 | クラウド保存していなかったため復旧不能 |
| シードフレーズを写真で撮っていた | クラウド同期→ハッキングで盗まれる |
ウォレット関連の重要な情報の違い
| 用語 | 内容 | 紛失時の影響 |
| パスワード | アプリやウェブウォレットへのログイン用 | 変更可能/再設定可能な場合もある |
| 秘密鍵/シードフレーズ | ウォレットそのものの復元キー | これを失うと資産に一生アクセス不能 |
| 2FAコード | 二段階認証アプリのコード | スマホ故障で使えなくなるとログイン不可 |
実例:数百億円分のビットコインが取り出せない
- 2021年、海外のあるエンジニアが秘密鍵を忘れてしまい、7,000 BTC(約300億円)にアクセスできないというニュースが話題に。
- 復元コードを10回間違えると完全ロックアウトというウォレット仕様のせいで、資産が事実上“永久凍結”状態。
対策①:パスワードやシードフレーズは複数の方法で安全に保管
おすすめの方法:
| 方法 | 特徴 |
| 紙に書いて保管(オフライン) | ハッキングリスクゼロ/ただし紛失に注意 |
| 金属プレート(防火・耐久用) | 火事・水害でも残る/高価だが信頼性◎ |
| USBメモリ or 外付けHDDに保存 | オフライン保管可能/ウイルス感染に注意 |
| 暗号化クラウド(高度な知識向け) | パスワード付きZipやBitwardenなど/利便性高いがリスクもあり |
避けたい方法:
- スマホの写真フォルダに保存
→ クラウド同期で盗まれる可能性あり - LINEやメールに送る
→ 通信経路から漏れるリスク大
対策②:リカバリーフレーズ(シードフレーズ)は絶対に失くさない
12〜24単語の英単語の羅列(例:sugar horse castle jungle …)がシードフレーズです。
- これがあれば、スマホが壊れても別の端末で復元可能
- 逆に言えば、これを失えば一生取り出せなくなります
対策③:ウォレットアプリによって復元方法は異なる
| ウォレット種別 | 復元に必要なもの |
| メタマスク(MetaMask) | シードフレーズ12語(ログインPWは変更可) |
| Trust Wallet | シードフレーズ12語 |
| Ledger / Trezor(ハード) | 24語+PINコード |
| 取引所ウォレット | ID/パスワード/2FA(サポートがある) |
対策④:定期的な“アクセス確認”と“保管チェック”を
- 半年に一度は、自分の保管方法を確認することをおすすめします
→ 紙が劣化していないか/クラウドに誰でもアクセスできる状態ではないか など
| 問題点 | 内容 |
| パスワードを忘れた | 一部アプリなら再設定可能だが、限界あり |
| 秘密鍵・シード紛失 | 完全に資産が失われる(誰にも復元できない) |
| 対策 | 紙+USBなどで分散・オフライン保管/家族に伝える方法も要検討 |
対策:複数の場所にバックアップ。クラウド保存よりもオフラインでの保管がおすすめ。
失敗例13:
レンディングで長期間資金をロックする
レンディングとは?
仮想通貨の貸し出しサービスのこと。
ユーザーが自分の仮想通貨を取引所やプラットフォームに預け、その資産が第三者に貸し出され、一定の利息(利回り)を得られる仕組みです。
- 年利3〜12%前後の利回りが期待できる
- 放置で増えるため“お得”に見えるが…
よくある後悔のパターン
ケース①:
- ETHを年利6%でレンディングに預ける(ロック期間:90日)
- その間にETHがニュースで急騰 → 価格が2倍に
- 売りたいけどロック中で引き出せず、結局高値を逃す
ケース②:
- 無名コインを高利回りに釣られて貸し出す(例:年利15%)
- 市場が急落 → 元本ごと戻らず
- プロジェクト側が倒産 → 資金も消失
初心者が陥る心理
| 心理 | 内容 |
| 「寝かせておくよりお得」 | 持っているだけなら、利回りで増やしたいという思考 |
| 高利回りに飛びつく | 「年利15%!」などの宣伝に弱く、詳細を読まずに預けてしまう |
| 価格の上下を見越していない | レンディング中に値上がりしても、身動きが取れないことを考えていない |
ロック型とフレキシブル型の違い
| 種類 | 特徴 | 引き出し可能? |
| 固定期間型(ロック型) | 7日、30日、90日などの期間中は引き出し不可 | ❌ 不可(契約満了まで動かせない) |
| フレキシブル型(可変) | 利回りは低めだが、いつでも解除可能 | ✅ 可能(ただし手数料がかかる場合も) |
対策①:ロック期間は必ず事前確認
- 解除不可期間の有無と長さを明確に確認(7日/30日/90日など)
- 一見高利回りでも、「その間に売れないリスク」があると考えるべき
対策②:レンディングに出すのは「使わない余剰資金」のみにする
- 価格変動時に売買する予定のコインはレンディングに出さない
- 例:長期保有目的のビットコインの一部だけをレンディングに活用
対策③:高利回りの裏には高リスクあり
特にDeFi系レンディングは要注意:
| プラットフォーム | 利回り | リスク |
| Binance Lending(中央集権型) | 年利2〜6% | 比較的安全、ロック期間あり |
| DeFi系(Aave, Compoundなど) | 年利5〜15% | プロトコルバグや価格変動リスクあり |
| 無名DEX/謎プロジェクト | 年利20〜100% | ラグプル・破綻・返金不可リスク大 |
対策④:「急騰したら売る」が前提の通貨はレンディングしない
- もし「このコイン、短期で上がるかも」と期待しているなら、いつでも売れる状態で持っておくべき
- レンディングはあくまで「使わない・しばらく動かさない」資産の活用先と考える
| 問題点 | 内容 |
| ロック中は売却できない | 急騰してもチャンスを逃す |
| 高利回りにはリスクが潜む | 無名プラットフォームは特に注意 |
| 対策 | 余剰資金でのみ活用/事前にロック条件を確認/分散投資を意識 |
仮想通貨レンディングは「利息がもらえる=安心」ではなく、
自由が制限される代わりに“ほんの少しリターンを得る”選択肢です。
対策:レンディングは使わない資金の一部だけ。途中引き出し不可の条件も事前確認を。
失敗例14:
トレンドに流されすぎて資金が分散しすぎる
よくある失敗パターン
- SNSで「今はSOL(ソラナ)熱い!」と見て買う
- 数日後、「次はARB(アービトラム)が来る!」と見てまた買う
- さらに「AI銘柄が爆上げ中」「ミーム系がアツい」…と次々に手を出す
- 気づけば10種類以上の通貨を保有
- 各通貨の値動きやニュースを追えなくなり、管理不能に
- チャンスを逃し、利確・損切りのタイミングもバラバラで非効率に…
なぜ資金が分散しすぎてしまうのか?
| 心理的要因 | 内容 |
| 置いて行かれたくない(FOMO) | 「みんなが買ってるなら、自分も乗らなきゃ」 |
| 全部上がりそうに見える | SNSでは“成功事例”ばかりが目に入るため |
| リスク分散と混同 | 本来のリスク分散ではなく、思考停止の“バラ撒き”投資になっている |
資金の分散=「悪いこと」ではないが…
本来のリスク分散とは:
- 相関性の低い資産に投資し、リスクを軽減する
- 数銘柄にしぼって、情報も定期チェックできる状態を保つ
悪い分散:
- 流行るたびに買い、戦略も計画もなく増やしていく
- 数が増えることで「どれをどこで売るか?」もあいまいになり、損益管理が困難
デメリット(リスク)
| 問題 | 内容 |
| 情報管理が追いつかない | ニュース、アップデート、価格変動などを日々チェックしきれない |
| 損切り・利確のタイミングが曖昧になる | 上がっても気づかない/下がっても判断が遅れる |
| パフォーマンスが平均化する | 大当たりがあっても、他で損して結果的にプラマイゼロになる |
対策①:「自分の投資可能銘柄数」を決める
- 初心者なら 3~5銘柄以内に絞るのがベスト
- 「自分でしっかりニュース・価格・ファンダメンタルを追える範囲内」にとどめる
対策②:投資チェックリストを作る
購入前に以下を確認:
・そのコインの目的(ユースケース)は何か?
・チームやプロジェクトの信頼性は?
・過去の価格推移や時価総額の安定性は?
・他に似たプロジェクトと比べて優位性があるか?
・「今」買う理由は明確か?(流行りだけじゃないか?)
→ このチェックリストを通らないコインには手を出さないと決めておくことで、無駄な分散を防げます。
対策③:「コア資産」と「サテライト資産」に分けて考える
- コア資産(BTC, ETH など):資産の中心、比較的安全性と実績のある通貨(60〜80%)
- サテライト(SOL, ARB, 個別銘柄など):話題性や期待値はあるが、リスクも高い(20〜40%)
→ こうすれば、「トレンド銘柄に乗る」こと自体はOKでも、全体がブレにくくなります
対策④:「売り時が明確なものだけ保有する」
- 保有目的が「上がるかも」だけなら売る基準も曖昧
- 「●%上がったら利確」「〇〇のイベント後に判断」など売却ルールが明確なものだけに厳選
| 問題点 | 内容 |
| 流行に流されすぎる | 気づけば銘柄が増え、管理不能に |
| 悪い分散は逆効果 | パフォーマンス低下/チャンス損失 |
| 対策 | 3~5銘柄に絞る/チェックリスト導入/ポートフォリオ構成を明確化 |
対策:投資銘柄は厳選して管理できる範囲内に。チェックリストを活用すると便利。
失敗例15:
仮想通貨詐欺やフィッシングに引っかかる
よくある詐欺被害のパターン
ケース①:高利回り詐欺
- SNSやLINEで「年利100%保証!このプロジェクトに投資しないと損」などの誘導
- 「今だけ!」「限定招待制」などの言葉で煽られ、よく分からないまま資金を送金
- 数日後、連絡が取れなくなる or サイトごと消滅
ケース②:フィッシング詐欺(偽サイトに誘導)
- 取引所やウォレットの「偽ログインページ」が出回っており、見た目は本物とそっくり
- ID・パスワード・シードフレーズを入力 → 即座にウォレットが乗っ取られる
ケース③:エアドロップ詐欺
- 「無料でトークンがもらえる」とDMや投稿で誘導 → 不審なリンクをクリック
- ウォレットを接続した瞬間、中身を全部抜き取られる
なぜ初心者は騙されやすいのか?
| 心理的要因 | 説明 |
| “楽して儲けたい”願望 | 年利100%、保証つき、紹介するだけで報酬…という甘い言葉に弱くなる |
| 知識が少ない | 本物のプロジェクトと詐欺の見分けがつかない |
| FOMO(乗り遅れたくない) | 「今だけ限定」「先着〇名」の言葉に焦って判断が甘くなる |
| 信頼しやすい | SNSで数万人フォロワーがいる=信用できると誤解しやすい |
被害にあいやすい詐欺の特徴
| 特徴 | 内容 |
| 高配当・保証・即金を謳う | 「必ず儲かる」「元本保証」は99%詐欺 |
| URLが微妙に違う | binance→blnance(小文字L)など巧妙に偽装 |
| ウォレット接続を強要 | メタマスクやTrust Walletに接続させて中身を抜く |
| 日本語や英語が不自然 | 怪しい翻訳文や文法ミスが散見される |
対策①:知らないリンク・DMは絶対に開かない
- SNS・Discord・Telegramなどで突然送られてくるリンクは100%疑ってかかる
- 「〇〇エアドロップ参加はこちら」なども基本無視でOK
対策②:公式URL・ドメインを自分で検索して確認
- 正しいURLはブックマークで保存し、毎回そこからアクセス
- 「Google広告経由」や「検索上位の広告枠」も偽サイトである可能性があるので注意
対策③:「ウォレット接続=リスク」だと心得る
- 信頼できないサイトでのメタマスク接続は財布の中を見せるのと同じ
- 「Approve(承認)」や「Sign(署名)」の操作は、資産移動の同意と同義になることも
対策④:誰にでも起こりうると自覚する
- 「私は騙されない」と思っている人ほど狙われやすい
- 仮想通貨詐欺は詐欺のプロ vs 知識のない個人投資家という戦い。
- 慎重すぎるくらいがちょうどいい
実際に起こった有名な詐欺事例
| 年 | 詐欺名/事件 | 被害概要 |
| 2020年 | PlusToken事件 | 約3,000億円以上が奪われたマルチ型ウォレット詐欺 |
| 2022年 | OpenSeaフィッシング | 偽メール経由でNFTが大量に盗まれた |
| 2023年 | Twitter仮想通貨ギブアウェイ詐欺 | Elon Musk風アカウントでBTCを送らせる詐欺が横行 |
対策:知らない人からのDMや不審なリンクは絶対に開かない。公式サイトやドメインを確認するクセをつけましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回紹介したように仮想通貨の世界では、小さな油断が命取りになります。
この記事で紹介した失敗あるある15選を確認し、自分はこのような過ちを犯さないようにぜひチェックしてください。
また、次回の記事では
初心者が失敗を避けるために絶対知っておくべきポイント
について紹介していきますので、こちらの記事も楽しみにしていただければと思います。