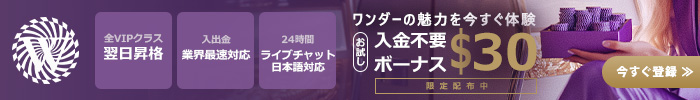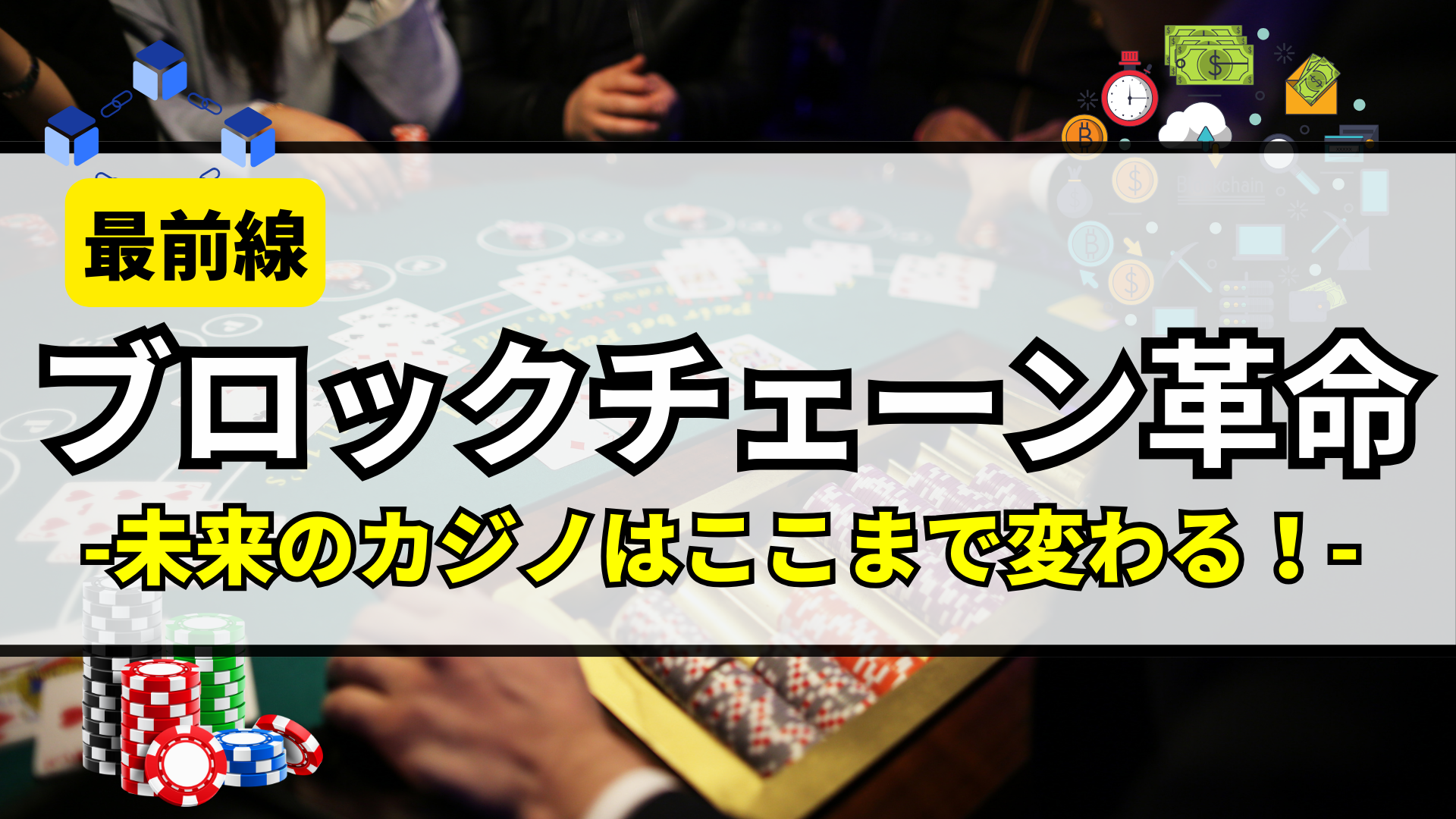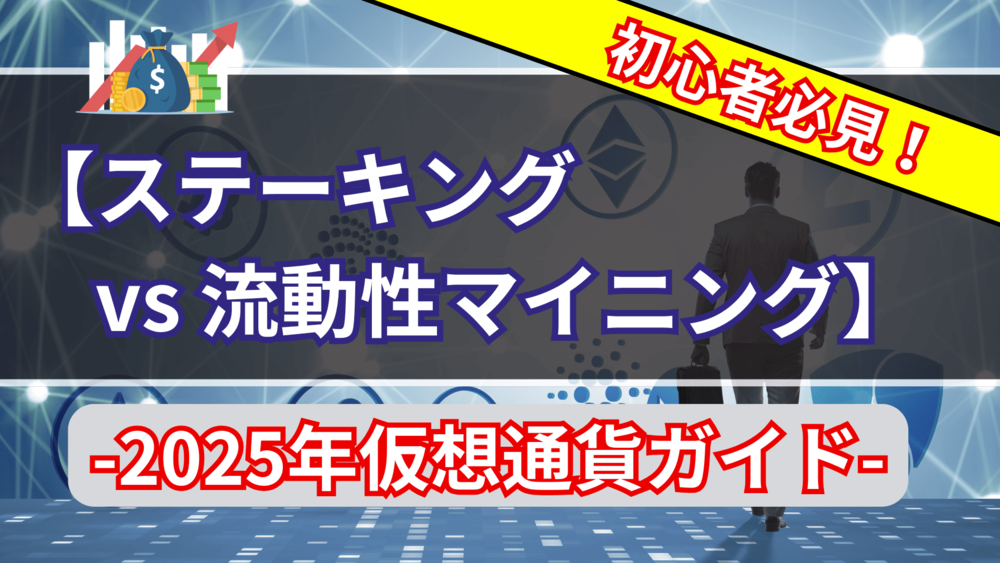仮想通貨を始めるうえで、
まず押さえておきたい基本用語をわかりやすくまとめました。
初心者の方はもちろん、
改めて整理したい方にも役立つ内容となっております。
以下より用語集をぜひご確認ください。
仮想通貨・クリプト
仮想通貨(暗号資産)
インターネット上でやり取りされるデジタル通貨の総称。ブロックチェーン技術と暗号学的手法によって、中央の管理者がいなくても安全性・信頼性が確保されている。国境を越えた送金、投資、契約などに活用される。
クリプト(Crypto)
「Cryptocurrency(暗号通貨)」の略語で、仮想通貨業界全体を指すスラング。使用される例として「クリプト投資」「クリプト市場」などの用語で使用される。
ビットコイン(Bitcoin / BTC)
2009年に「サトシ・ナカモト」によって生み出された最初の仮想通貨。中央銀行や政府を介さずに個人間での取引が可能な分散型デジタルマネー。供給量には上限があり、2,100万BTCまでと定められている。
イーサリアム(Ethereum / ETH)
スマートコントラクトと分散型アプリケーション(dApps)を可能にした第2世代の仮想通貨。ビットコインよりも機能的に多目的で、DeFiやNFTの基盤として広く利用されている。
サトシ・ナカモト
ビットコインの開発者とされる謎の人物またはグループ。未だに正体は不明で、誰であるか特定されていない。
ブロックチェーン
ブロックチェーン
分散型台帳と呼ばれる技術で、中央の管理者を置かずに取引履歴を多数のコンピュータ(ノード)に分散して記録・管理する仕組み。
各取引は「ブロック」としてまとめられ、過去のブロックと順番にリンクされて「チェーン」となる。改ざんが極めて困難で、透明性と信頼性の高いデータ管理が可能。ビットコインやイーサリアムなど、ほとんどの仮想通貨の基盤技術。
ブロック
ブロックチェーンに記録される1つのデータ単位。複数の取引(トランザクション)をまとめたパッケージのようなもので、タイムスタンプ、前のブロックのハッシュ、そして新しい取引の情報などを含む。
新しいブロックは一定時間ごと(例:ビットコインなら約10分)に生成され、前のブロックとつながってブロックチェーンを形成する。
ジェネシスブロック
そのブロックチェーンで最初に生成された、いわば“第1号”のブロック。
すべてのチェーンの基点であり、他のブロックはこのジェネシスブロックに続いて記録されていく。ビットコインのジェネシスブロックには、2009年1月3日の新聞見出しがメッセージとして埋め込まれている。
トランザクション(取引)
ブロックチェーン上で行われる「価値の移動」や「契約の履行」などの記録。例えば、ビットコインでは「AがBに1BTCを送金する」といった行為がトランザクションとなる。送金額・送信元・受信先・署名(本人確認のため)などの情報が含まれ、ブロック内に格納される。
ノード
ブロックチェーンネットワークに接続しているコンピュータのこと。
ノードはネットワークの安定性・セキュリティを支える重要な存在で、トランザクションの検証、ブロックの受信・送信・保存を行う。ノードが多いほどブロックチェーンの分散性と堅牢性が高まる。
フルノード
ブロックチェーンの全履歴(すべてのブロックとトランザクション)を保存し、ネットワーク上で新しい取引の検証を行うノード。
個人でも運営可能で、中央管理者がいないブロックチェーンの“監視員”として重要な役割を果たす。
ライトノード
ブロックチェーンの一部(例えば最新のヘッダー情報など)だけを保持し、必要なときにフルノードに問い合わせてデータを得る軽量ノード。
スマホ用のウォレットアプリなどで使われ、処理負担を減らしながらも基本的な機能は維持される。
マイニング&セキュリティ
マイニング(採掘)
新しいブロックを生成するための計算作業で、ブロック内の取引が正当かどうかを検証し、ネットワークに追加する役割を担う。
膨大な計算(ハッシュ計算)を最初に成功させたノード(マイナー)には、報酬として仮想通貨(例:BTC)が支払われる。これにより、ブロックチェーンの安全性とインセンティブの仕組みが両立されている。
ハッシュ
任意のデータから固定長の文字列を生成する「暗号化された指紋」のようなもの。
ブロック内の取引情報をハッシュ化することで、少しでも内容が変わると全く異なる値になり、改ざんが即座に検出可能となる。SHA-256というアルゴリズムが有名。
ハッシュレート
マイニング時に1秒間に実行できるハッシュ計算の回数。単位はH/s(ハッシュ/秒)。
ネットワーク全体のハッシュレートが高いほど、マイニング競争が激化し、安全性が高まる。個人のハッシュレートはPCやマイニング機器の性能によって変わる。
採掘難易度
マイニングで「正解」とされるハッシュを見つける難しさを示す指標。
ブロック生成のスピードが早くなりすぎないように、一定のブロック数ごとに難易度が自動調整される。ビットコインでは約2週間ごとに調整。
マイニングプール
個人や少人数では成功率が低いため、多くのマイナーが計算力を持ち寄って採掘する仕組み。
ブロックが生成された場合は、貢献度(ハッシュ計算数など)に応じて報酬を分配する。個人マイナーが安定的に報酬を得るための戦略として広く使われている。
ウォレット
ウォレット
仮想通貨を保管・管理するためのソフトまたはハード。実際には仮想通貨そのものではなく、秘密鍵を安全に保管し、取引時に署名を行うために使う。スマホアプリ、ブラウザ拡張、USB型など多様。
秘密鍵
資産の所有者であることを証明する最重要データ。送金の際に「自分が本物の持ち主です」と署名するために必要。紛失や流出は資産喪失に直結。
公開鍵
秘密鍵から数学的に導き出されるペアとなる鍵。他者に見せても安全で、暗号通信やアドレス生成に使われる。
アドレス
仮想通貨の送受信先となる文字列(例:0x〜やbc1〜など)。公開鍵を圧縮して作られる。銀行でいう口座番号にあたる。
シードフレーズ
秘密鍵を復元するための12〜24単語のパスワード。ウォレット紛失時の復元手段であり、これを盗まれると資産を奪われる。紙に書いての保管が推奨される。
ハードウェアウォレット
仮想通貨(暗号資産)の「秘密鍵」をオフラインの専用機器に安全に保管するためのデバイス。USBメモリのような見た目の物が多く、インターネットから切り離された状態で鍵を保管できるため、ハッキングリスクを最小限に抑えることができる。
ホットウォレット
常にネット接続されているウォレット。取引が即座に可能で利便性は高いが、ハッキングリスクもあり。
コールドウォレット
インターネットに接続されていないウォレットで、ハードウェアウォレットや紙に印刷された「ペーパーウォレット」などがある。ハッキングリスクがほぼゼロで、長期保管に最適。
スマートコントラクト
「◯◯が起きたら××を自動で実行する」といった条件付き契約をブロックチェーン上でプログラム化したもの。仲介者不要で、Ethereumをはじめとする多くのチェーンで採用。
トークン
ブロックチェーン上で発行されるデジタル資産。用途は通貨、ポイント、ガバナンス投票権など多様。Ethereumでは「ERC-20(交換可能型)」「ERC-721(NFT)」などの規格がある。
NFT(非代替性トークン)
「唯一性」が保証されたトークン。アート、音楽、ゲームアイテムなどに使われ、所有証明・売買履歴もすべてブロックチェーンに記録される。
取引所・トレード関連
DEX(分散型取引所)
UniswapやSushiSwapなど、中央の管理者がいない取引所。ユーザー同士が自分のウォレットから直接仮想通貨を交換できる。KYC不要で透明性が高い。
CEX(中央集権型取引所)
BinanceやCoinbaseなど、企業が運営・管理する取引所。初心者に使いやすく、法定通貨での入金やサポートが充実。ただし資産の保管は取引所任せとなる。
ガス代(Gas Fee)
Ethereumなどのネットワークで、取引やスマートコントラクトを実行する際に支払う手数料。ネットワーク混雑時は料金が大きく変動する。
運用・投資関連
ステーキング
PoS(プルーフ・オブ・ステーク)型ブロックチェーンで、保有通貨を預けてネットワーク維持に協力し、報酬を得る行為。長期保有者に向いた資産運用方法。
イールドファーミング
DeFi(分散型金融)のプロトコルを組み合わせて最も利回りが高くなるよう資産を配置する手法。ハイリスク・ハイリターン型のDeFi戦略。
レンディング
自分の仮想通貨を他人に貸し出すことで、金利収入(利息)を得る仕組み。AaveやCompoundなどのDeFiプラットフォームで利用可能。
エアドロップ
特定の条件(ウォレット保有、SNSシェアなど)を満たすユーザーに対して、新規トークンを無料で配布するキャンペーン。プロジェクトの知名度向上を目的とする。
チェーン分岐とアップグレード
ハードフォーク
従来のチェーンと互換性のないアップデートを行い、チェーンが分裂する現象。例:ビットコインから分岐したビットコインキャッシュ(BCH)。
ソフトフォーク
旧バージョンとの互換性を維持しつつ、ルールの変更や機能の追加を行うアップグレード。チェーンの分裂は基本的に起こらない。
組織・規制・詐欺
DAO(分散型自律組織)
人間の管理者を置かず、スマートコントラクトと投票によって意思決定を行う組織形態。運営の透明性と分散性が特徴。例:MakerDAO、Uniswap DAO。
DeFi(分散型金融)
銀行や証券会社のような仲介者を必要とせず、ユーザーが自らウォレットから金融サービスを利用できる仕組み。レンディング、取引、保険、デリバティブなどが含まれる。
ラグプル(Rug Pull)
開発者がプロジェクトの資金を持ち逃げする詐欺行為。DeFiやNFTの世界で発生しやすく、事前の調査(DYOR)が重要。
KYC(Know Your Customer)
取引所や金融サービスでの本人確認手続き。ユーザーの身元確認により、不正取引やマネーロンダリングを防ぐ。
AML(Anti Money Laundering)
マネーロンダリング(資金洗浄)防止のための規制・法律対応。取引の監視や報告、顧客情報の保持などを含む。
情報と供給調整
ホワイトペーパー
仮想通貨プロジェクトが投資家や開発者に向けて発表する設計書・事業計画書。内容にはビジョン、技術仕様、トークン設計、スケジュールなどが含まれる。
トークンバーン
特定のトークンを「使えない状態にする」ことで、供給量を減らして価値の希薄化を防ぐ。インフレ対策や需給調整の一環。
相互運用・技術拡張
サイドチェーン
メインチェーンとは別の独立したブロックチェーンで、一定の条件のもと相互通信が可能。処理を分散させて全体のスケーラビリティを改善する役割を持つ。
DEXアグリゲーター
複数の分散型取引所のレートを比較して、最も有利な条件で取引を実行するサービス。ユーザーは最適な価格で仮想通貨を交換できる。例:1inch、Paraswap。
インターチェーン
異なるブロックチェーン間で、データや資産のやり取りを可能にする仕組み。相互運用性(インターオペラビリティ)を実現するための中核技術。
オラクル
スマートコントラクトにブロックチェーン外の情報(例:価格、天気、スポーツ結果)を提供する仕組み。外部データがなければ多くのDeFi機能が動かない。
レイヤー2(Layer2)
EthereumなどのL1ブロックチェーンの処理能力を補うためのサブレイヤー。ガス代削減や高速処理を実現する。例:Arbitrum、zkSync。
ゼロ知識証明(ZKP)
「内容を明かさずに、それが正しいと証明できる」暗号技術。プライバシー保護、本人認証、L2スケーリングで注目されている。
暗号学
情報の安全性・正確性・改ざん防止を担保する数学分野。ブロックチェーンの署名、ハッシュ、証明などの基礎技術を支える。
まとめ
以上、仮想通貨の基本的な用語となります。これから仮想通貨の勉強をする、または勉強をしている方も確認としてぜひようを一通り見ていただき、知らない用語がないか確認してみてください。そして、この記事がさらなる仮想通貨の理解につながっていければと思っております。
また、仮想通貨についての記事はこちらでまとめておりますので、よろしければ、こちらの記事一覧もご確認いただけますと幸いです。